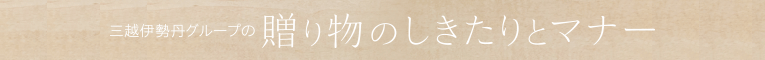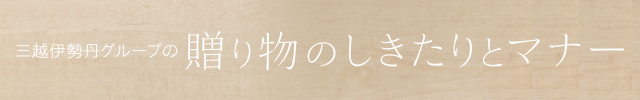神式
神式の流れ

通夜祭
神道では“死を穢れ”と考える死生観があります。そのため通夜や葬儀に神社は使わず、斎場か自宅で執り行います。数珠は使わず、「ご冥福」や「供養」などの言葉も使いません。「御霊前」は「みたまえ」と呼びます。
しきたりとマナー
神道では仏教の通夜にあたる式を“通夜祭”と呼びます。近親者や親しい友人、知人以外の一般の会葬者は、通夜祭か、仏式の葬儀(告別式)にあたる葬場祭(そうじょうさい)のどちらかに出席することが多くなっています。仏式の通夜ぶるまいにあたるものは“直会(なおらい)”と呼びます。死の穢れを忌むために、喪家では煮炊きをせずに外から運んだものでもてなします。
豆知識
神棚封じ/神様は人の死を忌み嫌うので、神棚を祀ってある家は、お祀りをする神棚に穢れのないよう、忌明けまで白い半紙などを貼って封印します。これを“神棚封じ”といいます。この間は普段の礼拝ができません。
Q&A
-
- 神道のお焼香はどのようなものですか?
- 仏式の焼香にあたるのは“玉串奉奠(たまぐしほうてん)”です。玉串とは神木である榊の枝に、木綿(ゆう)や紙を細長く切って下げたもの。玉串を捧げるときは、二礼ののちに、音を立てないように拍手を二度打ちして(しのび手)一礼します。
-
- 不祝儀袋の表書きは神式でも御霊前でいいですか?
- 水引は黒白、双銀、黄白のま結びで、表書きは「御玉串料」がもっともよく使われます。やや高額の場合は「御榊料(おさかきりょう)」も使われます。「御霊前」も使いますが“みたまえ”と読みます。不祝儀袋は蓮の花のついていないものを使います。
-
- ご返礼はどのようにしたらよいでしょうか?
- 五十日祭の日以降、挨拶状を添えて返礼を行います。ご返礼の目安は、いただいた額の三分の一から半分を返すのが一般的です。
葬場祭
神式で行われる葬祭儀式を総称して神葬祭と呼びます。死者を命(みこと)とあがめ、祖先の神々とともに家の守護神として祀るための儀式です。
しきたりとマナー
人の死のことを仏式では「永眠」と呼びますが、神式では「帰幽(きゆう)」といいます。「ご冥福」「供養」「回向」「冥土」なども仏教用語なので使いません。祭式に入る前には、“手水の儀(ちょうずのぎ)”といって、必ず手水を使って身を清め、口をすすぎます。ただし自宅で葬儀を行う場合、手水の儀を省略することもあります。
豆知識
供物とは/神仏や先祖、故人の霊に対して供え奉るものを供物(くもつ)といいますが、仏式では“焼香”し、神式では“榊”をたむけ、キリスト教式では“花”を献ずることを基本としたことから、各宗教によって“お供え”と関連していると考えられます。
霊祭
神式では仏式の法要のことを“霊祭”と呼びます。霊祭は葬儀翌日の翌日祭、十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭、五十日祭と、十日ごとに行うのが正式です。しかし現在では、五十日祭に神官を招いて霊祭を行うことが多いようです。百日祭以降の霊祭からは式年祭と呼びます。五十日祭の時の表書きは「偲び草」か「志」(黄白)と記載します。
しきたりとマナー
式年祭は一年祭、三年祭、五年祭、十年祭と続き、その後は五十年祭まで十年ごとに行われます。神官の方を招いて行うのは、一年祭、三年祭(満3年)、五年祭(満5年)、十年祭(満10年)が一般的です。霊祭には、親しい方や親戚から酒、鮮魚、果物、野菜、乾物などの海の幸や山の幸が供えられることが多く、これに菓子折りなどが加わるようです。一般の方からは金子包みを持参するケースがよくみられます。
Q&A
-
- 十年祭の引き物はどんなものがよいですか?
- 霊祭の引き物は、仏式の引き物と同様でよいでしょう。煎餅、クッキー、コーヒー、ようかん、鹿の子、お茶、椎茸、海苔、紅茶、タオル、ハンカチ、バス&シャワー用品など 持ち帰りやすい、かさばらない食べ物や日用品が適しています。