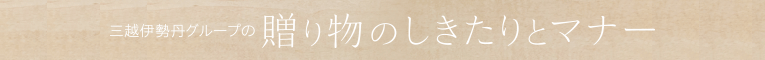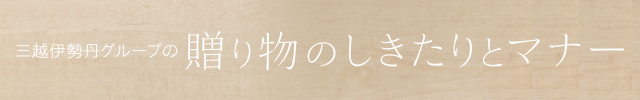季節のご挨拶
冬の贈り物(お歳暮など)
歳暮とは、文字通り年の暮れのこと。季節を表す言葉に「お」がついて、年末の贈りものを意味するようになりました。百貨店でもインターネットによるお歳暮の受注などを受け付けているので、自宅にいながら都合のよいときに簡単に申し込みができます。毎年の決まりごとではありますが、毎回、贈る先さまのことを考えて選びたいものです。
しきたりとマナー
お歳暮を贈る時期は、本来は“事始めの日(正月を祝う準備を始める日)”である12月13日から20日までの間でしたが、現在では12月初旬から12月25日頃までに贈るのが一般的です。最近では11月下旬から贈り始めることもありますが、本来の意味を考えると、12月に入ってから先さまへ届くようにしたいものです。時期が決まっていることなので、感謝の気持ちを込め、余裕をもってゆっくり品選びをしましょう。お歳暮は日頃お世話になっていることへのお礼なので、基本的にお返しは不要ですが、マナーとしてお礼状は出しましょう。
贈り方



-
●お歳暮の贈りもの
◎紅白もろわな結びののし紙
◎のし付短冊<表書きの種類>
御歳暮、お歳暮 -
●冬の贈りもの
◎紅白もろわな結びののし紙
◎のし付短冊<表書きの種類>
御年賀、お年賀(元日~1月7日・関西1月15日)、
寒中御伺(1月8日・関西1月16日~立春前日の2月3日頃)、
余寒御伺(立春の2月4日頃~2月末日まで)
Q&A
-
- お歳暮に食べ物が多いのは昔の習わしですか?
- 他家に嫁いだ娘が正月の歳神様に供える祝い肴(新巻鮭、ブリなど)を実家に贈った習わしが残り、暮れの贈答品として新巻鮭などがよく用いられたようです。また、戦前は米、野菜、魚、鏡餅、酒などの神棚にお供えするものをお歳暮としていたことから、食べ物を贈る習慣となったともいわれています。
-
- 先さまが喪中の場合、お歳暮を贈れますか?
- 喪中は通常1年間ですが、現代では忌明け(四十九日)を過ぎていれば、お歳暮を差し上げてもかまわないとされます。
-
- お歳暮を年内に届けられないときはどうしたらいいですか?
- 松の内(関東は1月7日、関西は1月15日)が過ぎてから「寒中御伺」として贈りましょう。立春(2月4日頃)の前日までに贈ります。