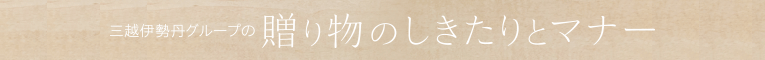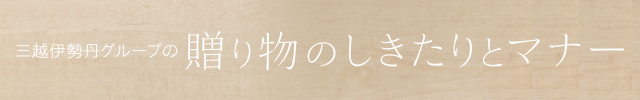贈り物のマナー
表書きと名入れ
贈りものをするとき、のし紙やかけ紙に表書きをします。表書きにはさまざまなものがあります。大切なのは贈り主の誠意とまごころが伝わることです。贈る相手や目的、自分の気持ちに合わせて選びましょう。
しきたりとマナー
表書きは、贈りものの目的を表すものです。そのため書き入れるのが一般的ですが、手土産などを直接持参する場合に「包装紙だけでは味気ないので、もう少しあらたまった形にしたいけれど、仰々しくはしたくない」というときには、紅白もろわな結びののし紙だけをかけることもあります。日本人の美徳の一つである奥ゆかしさから「粗品」という言葉もありますが、大切な贈りものにつける表書きにはふさわしくありません。「寸志」や「薄謝」も同様で、贈りものには「御礼」「お礼」「謝礼」などとするほうが自然でしょう。なお「寸志」や「薄謝」は、原則として立場や年齢が高い人などから年下や後輩にあたる人などに贈る場合に使う言葉です。
贈り方
| 贈り物の目的 | 表書きの種類 | 解説 |
|---|---|---|
| 一般的な 贈りもの |
こころばかり | 「わずかなものですが、お受け取りください」という気持ちを込めて、ささやかな贈りもののときに使う。中元・歳暮などの季節のごあいさつ代わりにも使われます。 |
| 御挨拶 | 文字どおり、ごあさつの印として贈るときに使う。引っ越しなどで使われることが多いです。 | |
| 御伺 | ごあいさつ、あらゆるお見舞いに使う。特に目上の方への病気見舞いに使います。 | |
| 松の葉 | 松の葉にかくれるくらいの、こころばかりの品、あるいは金額という意味。地域によっては引出物のひとつに使われます。 | |
| まつのは・ みどり |
どちらも松の葉と同じ意味。主に女性が使います。 | |
| 公的な 贈りもの |
寄贈・贈呈・贈 | 会社や団体などに、あるいは団体から団体(学校など)へ品物を贈るときに使う。大きなものを贈るときには、目録を用意し、こうした表書きをします。 |
| 立場や年齢が高い方への贈りもの | 謹呈 | 謹んで贈呈するときに使います。 |
| 進呈 | 同輩などにも使われます。 | |
| 謝礼を したいとき |
御禮 (おんれい) |
旧字体の“禮(れい)”を使うことで、より丁重な感じになります。 |
| 御礼・お礼 | 一般的なお礼のとき。「お礼」のほうがより気軽。 | |
| 感謝 | 感謝の心で金品を贈るときに使います。 | |
| 謝礼 | こころづけ、お礼などのときに使います。「大変お世話になりました」という気持ち。 | |
| 謹謝 | 謹んで感謝の気持ちを表すときに使います。 | |
| トラブル | 御詫び・お詫び・御挨拶・ご挨拶・粗品 | 交通事故で加害者が被害者を見舞うときに使います。 |
| 御挨拶・ご挨拶・御詫び・お詫び・粗品 | 工事のときの隣近所へのあいさつ、苦情へのお詫びのときに使います。 | |
| 御挨拶・ご挨拶・御詫び・お詫び・粗品 | 火元としてのお詫びのあいさつのときに使います。 | |
| 神仏に 供えるとき |
御寄進 (ごきしん) |
神社仏閣に寄付などを贈るときに使います。奉納と同じ意味。 |
| 御供 (おそなえ) |
神仏に品物を供えるときに使います。 | |
| 神事・奉納のとき | 奉納 | 神に対してうやうやしく金品を捧げるときに使います。 |
| 奉献 | 神前に酒を供えるときに使います。 | |
| 御神前 | 神のみたまに奉げる意で神事全般に使います。 | |
| 御玉串料・ 御榊料 |
神前でお祓いを受けたお札、またはお祓い料として使います。 | |
| 御初穂料 | その年の最初の米を供えるという意味。お宮参り、結婚式などの慶事のお礼に使います。 | |
| 御祈祷料 | 厄払いや合格祈願などのお礼に使います。 | |
| 御神饌料 (ごしんせんりょう) |
神に供える神饌のかわりの金子包みに使います(神饌とは神に供える米・餅・魚介・海藻・野菜・果物・菓子・塩・水・酒など) |
<名入れ>

-
●贈り主の名前の書き方
名前は表書きの字よりもやや小さく入れます。
一般的には、姓名を書きますが、個人名よりも家の名が適当な場合は姓だけ書くこともあります。

-
●会社名や肩書きを入れる場合
文字の大きさは、次の順にしたがい小さくしていく。
①表書き
②氏名
③会社名
④役職名

-
●夫婦連名の場合
夫が右(姓名)妻が左(名)に書き入れます。

-
●連名の場合
立場や年齢が高い方の姓名を中央から左へ順番に書き入れます。連名で3名程度までとします。

-
●連名で代表の姓名のみを入れる場合
代表で中央に太く書き、左側に外(他)一同と小さく入れます。