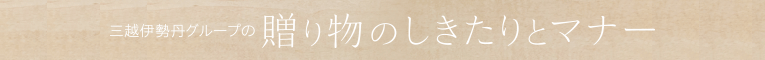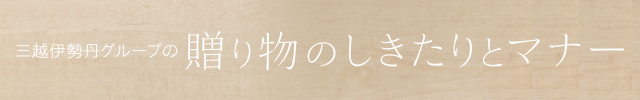ご利用ガイドTOPへ戻る
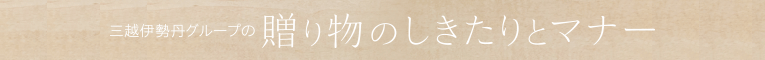
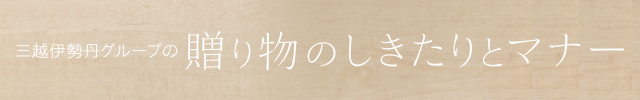
贈り物のマナー
Q&A

Q&A
-
- 水引は何色で何本ですか?
- 鎌倉から室町時代までは白一色でした。やがて紅白、金銀、黒白、黄白、青白などの染め分けや、双金、双銀の一色のものも使われるようになりました。現在では、一般の贈答や慶事には紅白の水引を用い、結婚祝いのように特に華やさを表す場合や、高価なものを贈るときなどは金銀の水引も用いられます。弔事では黒白や黄白の水引を使うのが一般的です。本数は、用途や包みの大きさ、金額などによって異なります。3本、5本、7本と奇数のこよりを束にして使うことが多く、中でも5本1組で使うことが多くなっています。
-
- かけ紙の裏側の止め方と、水引の結び方を教えてください。
- かけ紙は左から閉じて、右側を上にして止めます。ただし、かけ紙の右、あるいは左すみに社名やロゴが印刷されている場合は、それを優先して上にあわせることが多いです。水引の結び方は、裏側のちょうど中央に紅白、金銀の境目がくるようにし、表側は向かって左側に白や銀がくるようにして結びます。
-
- 短冊はどのようなときに使いますか?
- 贈りものの中には、慶弔をはっきり表したくないものや、お見舞いなど慶弔どちらにも属さないもの、控えめにして相手に負担をかけたくないものも多くあります。その場合は細長く切った紙の小片である短冊を用いてもよいでしょう。短冊は物理的にかけ紙をかけにくい場合にも用います。のし付と無地があり、一般の贈答や慶事、お礼などはのし付、お見舞いや弔事、お詫びなどは無地を用いるのが一般的です。
-
- 一つの品物に「御礼」と「御祝」、「結婚祝い」と「出産祝い」などののし紙を一緒につけてもよいですか?
- 本来別々の意味があるものを、一度で済ませるという考え方は、先方に失礼と受け取られても仕方ありません。一つの品物に二つののし紙をつけるものでもありません。それでもどうしても一品に二つの意味を込めたい場合は、どちらかの気持ちののし紙を付けて、もう一つの気持ちについてはメッセージカードなどで伝えるとよいでしょう。お祝いごとが続いた場合は、最近あった出来事のほうを優先させます。そのため、結婚祝いと出産祝いでは出産祝いを優先、そのほか卒業祝いと就職祝いでは就職祝いを優先するということが多くなっています。ただし、先さまと贈る方との関係や事情、気持ちによって、どちらを優先してもかまいません。
-
- 外のし、内のしとはなんですか?
- 従来のし紙は、品物を奉書紙で包んで水引をかけるので、必然的に“外のし”になります。現在は印刷ののし紙ですが、そのかけ方は、贈りものを包装紙で包んだ上からのし紙をかける“外のし”が基本です。ただし、百貨店などを通じて届ける場合には、配送伝票を貼るので、贈りものの箱に直接のし紙をかけ、その上から包装紙で包む“内のし”にすることがほとんどです。
-
- 「寿」「内祝」「志」「上」はどう使い分ければよいでしょうか?
- 「寿」は、お祝いごと、めでたいことに際し、喜びを表すときに言葉で祝うことです。「いく久しくめでたさを祈る」という気持ちで、結婚、長寿などの慶事全般に使います。
「内祝」は、結婚祝い、出産祝い、長寿祝い、新築祝い、そのほかさまざまなお祝いごとが済んだあとのお返しに使います。本来は自祝いとしてささやかなお祝いごとをしたという意味なので、お返しだけでなく、お祝いに感謝する気持ち、お祝いごとを祝ったあとに「おかげさまで」「どうぞよろしく」の気持ちも込めて贈ります。
「志」は、もともとは好意や誠意などの気持ちをあらわす贈りものに使われていました。現在では、お悔やみをいただいたお返し、死者への供養、遺族の気持ちを込めた贈りものなどの弔事に広く使われます。
「上(じょう・うえ)」は、立場や年齢が高い方、神仏、先祖に対するときに使います。
-
- 「深謝」にはどういう意味がありますか?
- 「深謝」には、心から深く感謝すると深くお詫びするという意味があります。
-
- 表書きを書くときの墨の濃さの使い分けや、文字の書体や字体はどうすればよいでしょうか?
- 墨の濃さは、慶事は濃く、弔事は心持ち薄く書くのが一般的です。そもそも相手の名前などを書く際は、濃い墨で書くことが丁寧とされてきましたが、濃い墨色は目に強く映ることがあります。そのため弔事では「涙で文字が薄くなった」「墨をする時間も惜しんで駆けつけた」という意味を込め、薄墨が多く用いられるようになりました。のし紙やかけ紙、祝儀、不祝儀袋に書く文字は筆や筆ペンで書きましょう。書体は崩しすぎず、楷書か行書くらいの新字体で読みやすく書きます。ただし儀礼を重んじて、一部旧字体を使う場合もあります。主なものは「壽(ことぶき)」「御禮(おんれい)」「御靈前(ごれいぜん)」などです。文字は、のしや水引にかからないように注意します。