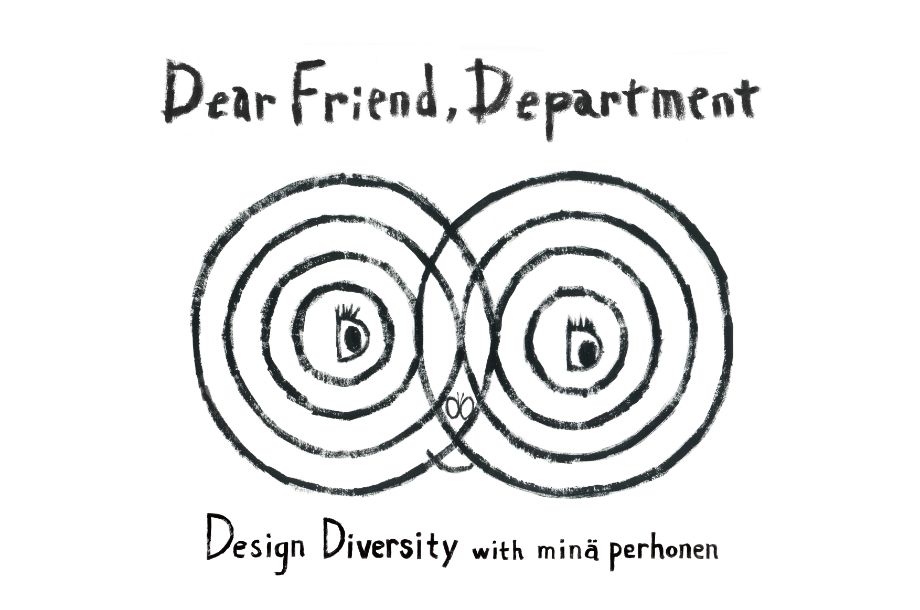皆川 明インタビュー|テーマは「Design Diversity」。

2018年、2021年につづき、3度目の開催となる「Dear Friend, Department」。今回は「Design Diversity」をコンセプトに掲げ、多様なブランドとコラボレーションを行った<ミナ ペルホネン>のデザイナー 皆川 明さんに、イベントに込めた思いを伺いました。
時代の空気を大切に、百貨店を見つめ直す
「Dear Friend, Department」
―「Dear Friend, Department」は2018年の初回から数えて3度目を迎えますが、あらためてこの企画をはじめた当初の思いを聞かせてください。
皆川 明さん(以下、皆川):当時はちょうど、百貨店のあり方や意義のようなものが社会的に問われるようになったタイミングでした。僕自身、子どもの頃は、百貨店に行くというのが特別な「ハレの日」だったわけですが、その頃にくらべると商品やブランドがクローズアップされるようになって、みんな百貨店の空間そのものの楽しさを忘れかけているんじゃないかと感じていたんです。ただ買物をするというだけでなく、家族のハレの時間をもう一度百貨店で楽しめたらおもしろいんじゃないか。そう考えたのがきっかけです。
―2021年はコロナ禍での開催となりました。「愛着と暮らす。」というテーマでしたね。
皆川:家で過ごす時間が長くなったことで「暮らす」ということへの関心が高まってきましたよね。短いサイクルで消費することが当たり前だった空気から、ものと出合い、暮らしの中で長く使うという意識に変化したように感じます。そのなかで、長く付き合えるデザインをご提案できたらと思いこのテーマを掲げました。

多様性を大切にする社会のなかで、デザインはどうあるべきか
―そして今回は「Design Diversity」というテーマですが、どういった思いから生まれたコンセプトですか?
皆川:「Dear Friend, Department」の最大の魅力は、伊勢丹の各フロアのみなさんと一緒にものづくりができるということ。暮らしのあらゆるシーンをご提案できるという意味でそれだけで十分多様性があるわけですが、いま世の中で大切にされているダイバーシティは、人種、性別、その他さまざまな環境の異なる人々が、互いを理解しあい、つながりあうこと。そのなかでデザインというものがどのようにあるべきか、どのようにあれば楽しいかを考えたとき、いろいろな地域、いろいろな歴史、いろいろなブランドのフィロソフィーが多様につながりあうことをテーマにしたいと考えました。

皆川 明さんによるキービジュアル。人の暮らしとデザインがつながりあい、重なり合っていく様子を表現した。
確固たる理念がありながら、新しいことに柔軟なスタンス
―多様なつながりということで今回たくさんのブランドとコラボレートされていますが、ものづくりにおいて意識されたことはありますか?
皆川:僕が本当にすばらしいと思うブランドに声をかけさせていただいたわけですが、もともとある良さはそのままに、<ミナ ペルホネン>というエッセンスを加えてどのように新しい視点をお届けできるかが一番のテーマでした。そのためにまず取り組んだのは、それぞれのブランドの理念、歴史、製造プロセスを理解すること。実際に工房を見せていただいたり、素材に対する考え方を伺ったり、そういった交流ができたことは僕自身にとってもすばらしい体験でした。
―コラボレートするうえで印象的だったエピソードなどあれば教えてください。
皆川:すべてのブランドにおいて、長年培われた確固たる理念がありながら、コラボレーションという取り組みに対して非常に柔軟であることが印象的でした。ずっと変わらずに守ってることがありながら、変わらないということではない。さまざまな課題をクリアしながら、新しいことに取り組んでいただける姿勢に毎回感動しています。
たとえば<ヴァレクストラ>は個人的にも愛用しているブランドですが、初期のバッグといまのバッグにたしかなつながりを感じるんです。一回一回新しいものを開発するのではなく、自分たちがつくったものをさらにブラッシュしていく。長年培ったものを更新していこうというスタンスや、職人ファーストな空気を感じました。僕らもひとつ生んだデザインを継続的に発展させたり、新しい視点で組み直したりというものづくりをしているので、テキスタイルと革という素材の違いや歴史の違いはあれど、ものづくりやデザインの視点では共通点を感じています。

これからも、人の暮らしとデザインの接点を生み出しつづけたい
―今回「Design Diversity」というテーマで取り組んだことでの気づきや、これからチャレンジしたいことなどありますか?
皆川:「Design Diversity」を掲げたことで、以前より深くものづくりに入り込んだコラボレーションが実現しました。プロダクト自体のダイバーシティが表現できたあとは、その生産背景におけるダイバーシティにも取り組んでいけるのではないかと思っています。それは、いろいろな人が働ける環境であったり、いろいろな地域で生産できるということであったり。物流の問題が大きくなっているいま、デザインを生み出す製造プロセスがレシピ化されて、さまざまな場所で同じものが生産できるようになれば、物流に頼ることなく世界の人が同じデザインや品質を手に入れられる未来がやってくるかもしれません。そういった、人の暮らしとデザインの接点を生み出すことを考えていきたいですね。

―ありがとうございました。さいごに、今回の「Dear Friend, Department」をどのように楽しんでいただきたいか、お客さまにメッセージがあればお願いします。
皆川:今回はたくさんのコラボレーションをご用意しているので、まず一度目はご自身の一番関心のあるアイテムに注目してください。そして、できれば二度三度足を運んでいただいて、「あの商品と自分の暮らしはどうつながるんだろう」と想像しながら見ていただけると新しい発見があると思います。みなさんの暮らしのなかには、日常もあれば、旅をされるような特別な体験もあるはず。「このシーンではこのデザインといっしょに過ごそう」なんてことを想像しながら楽しんでいただけたらうれしいです。